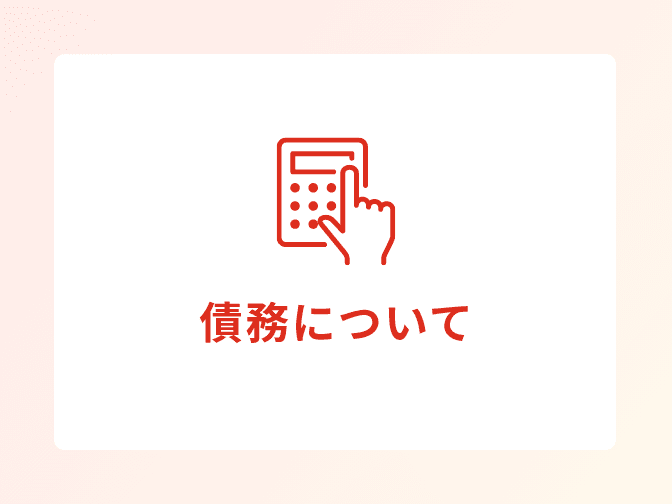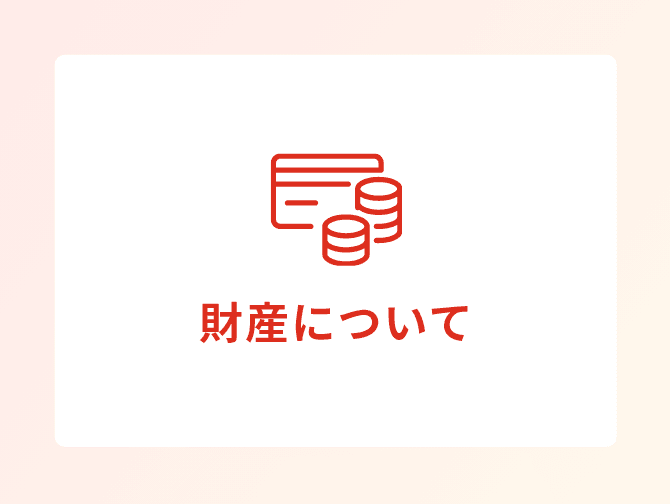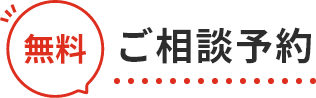個人再生手続における不同意意見の実例と対策
個人再生手続における不同意意見の実例と対策
小規模個人再生手続では、再生計画案の支払額及びその方法について、裁判所が債権者に意見をもとめます。
このとき、「頭数」又は「債権額」の過半数の債権者から反対の意思表示がされない限り、再生計画案は認可されます。
実際の案件では、ほとんどの債権者は再生計画案に反対せず、そのまま再生計画が認可されます。
しかし、一部の債権者は、再生計画に反対の意思表示(不同意)を示します。
債権者が再生計画案に反対の意思を表明するのはどういうときか、
反対されたとき、申立側は何ができるのか、
反対の意思表示が提出されないように事前対策が可能か、
今回の記事では、債務相談の際によく聞かれる質問について、当事務所の経験を交えて解説いたします。
【目 次】
1 不同意意見の理由
2 不同意意見の実例とその背景
3 債権者の不同意意見と対策
(1)不同意意見が再生手続きに与える影響
(2)債権者が不同意意見を提出した際の対策
(3)債権者が不同意意見を提出しないようにする事前対策
4 まとめ
1 不同意意見の理由
反対する債権者は「再生計画案に同意しない」という書面を作成し、裁判所に提出する必要があります。多くの金融機関、貸金業者は意見書を出すことはしません。
逆に、不同意意見を表明するケースには、以下3つの理由いずれかによるものが多い印象です。
個人的感情/借入・返済状況を考慮したうえでの個別判断
弁済額が上がることを期待している
反対する方針で全件対応している
以下、実例を交えて詳細を説明いたします。
2 不同意意見の実例とその背景
個人的感情/借入・返済状況を考慮したうえでの個別判断
知人、友人、取引先から預かったお金を投資で失敗して返せなくなったり、交際関係にあった際の借入金、会社経営や営業上の経費等の未清算金など、個人再生では、個人が債権者になる場合があります。そして、債権者が強い被害感情を持っている場合には、再生計画に反対されやすいです。
また、短期間のうちに高額の借入れを行い、ほとんど(又は一度も)返すことなく再生による減額を求めた場合などは、最初から返すつもりはなかったのではないかと債権者に判断され、再生計画に反対される可能性があります。
極端な例でいえば、再生債務の大半が直前の借入れによるもので、かつほぼ全てがギャンブル、FX・仮想通貨による損失の場合、仮に債権者が反対しなくても、裁判所から再生を受けつけてもらえない可能性があります。当事務所では、そこまで極端な例の申立てを行ったことはなく、受付を拒否された例は未だありません。
弁済額が上がることを期待している
個人再生手続は、債権者と個別に交渉して返済額を決めることなく、法律の基準にしたがって一定の弁済率の返済を提示すれば、減額が認められる点で画期的な制度です。そのため、一部の債権者から「もっと返せるはずだ」と意見されたとしても、原則としてはその意見には応じることはなく、決まった弁済率で再生計画を作成します。
ただし、総債務に占める割合が過半数に達する債権者(たとえば総債務600万円の事件において、1社で300万円以上の貸付のある業者)であれば、反対の意思表示をすれば再生手続きが認可されません。一部の債権者は、債権額が過半数を超えている場合にのみ反対することがあります。
なお、貸金業者が反対する場合、「弁済率は30%以上にすべき」など具体的な要求を伴うことはありません。事前の予告なく突然「再生計画に同意しない」との意見を表明してくることが殆どです。
反対する方針で全件対応している
会社や団体の方針として「債務の減額、免除には協力しない」という方針を固めている会社や団体があります。これらの会社や団体に対する債務を含む再生計画を提出した場合、対象となる債権者から不同意意見が出る場合があります。
これまでも、政策金融公庫や保証協会などの準公的な団体は、自身が過半数債権者かどうかに関係なく一律に不同意意見を提示するケースがありました。近年ではこれらの団体から不同意されることは少なくなっているように感じます。
むしろ、一般の貸金業者において、その業者が過半数債権者である場合は確実に不同意意見を提出し、不同意意見を提示することで債権回収額が増加するか試しているかのようなケース(楽天カード)が少し増えています。こうした傾向は債権回収会社などにも一部みられます。
3 債権者の不同意意見と対策
(1)不同意意見が再生手続きに与える影響
冒頭に示したとおり、債権額の過半数以上を単独で有する債権者が不同意を提出した場合、または頭数で過半数以上の債権者が不同意意見を提出した場合、当該不同意意見が撤回されない限り、再生計画案は棄却されて再生手続きは終了します。
(2)債権者が不同意を示した際の対策
不同意意見が出された場合、裁判所から申立代理人に対し「不同意意見が提出されました」と連絡を受けることがあります。
不同意意見が債権者から提出された時点では、ただちに再生計画が廃止されるわけではありませんので、不同意意見が過半数を超えている場合でも、個別に申立事情を説明することで不同意を撤回してもらえることもあります。
ただし、不同意意見が出た後であわてて検討、対策に移るのでは時間がなさすぎることも多いです。あらかじめ対策ができる場合には、それをしておくに越したことはないでしょう。
(3)不同意意見への事前対策
個人的感情/借入・返済状況を考慮したうえでの個別判断
被害感情のある個人債権者について、反対意見が債権額もしくは頭数で過半数を超えそうな場合、あらかじめ再生手続き全般の内容や、申立人の収入、資産状況を先に説明したうえで、再生手続きへの協力を求めておくことが考えられます。
貸金業者については、直近の借入額が特に大きい方や、借りてから殆ど返せていない方の場合、不同意されるか気になる事案もあります。しかし、事前に同意してくれるのか意向を調査しても、ほとんど回答してもらえません。
個別に申入れすることで、かえって債権者の調査が厳しくなり不同意のリスクが上がる可能性も考えられます。事案によっては、再生に至った事情を事前に説明したうえで意向調査する場合もありますが、意向調査せずそのまま申立てる事案もあります。
弁済額が上がることを期待している場合
弁済率に不満を持つ場合、債権者が個人か業者かによって問題となる箇所が異なる場合があります。
個人債権者の場合、例えば10%の弁済率が20%に増えたとしてもやはり不満を残される(100%払わないと納得しない)場合もあり、事前に意向調査しても、債権者の要望には応じられないこともあります。
貸金業者等の場合、給与所得者等再生を行った場合との弁済率の違いを気にすることがあります。言い換えると、借入時の収入を基準にすれば、再生計画案よりももっと多く返せるのではないかと判断される場合があるということです。ここは難しいので詳しく説明します。
個人再生には、同意/不同意の意見を求める「小規模個人再生」手続き以外に、2年分の可処分所得を払えば裁判所が再生を認可する「給与所得者等再生」もあります。この給与所得者等再生によれば弁済率が上がることが見込まれる事案の場合、貸金業者が不同意する例がまれにあります。(前述の楽天カードのほか、(株)ドコモ・ファイナンス(旧社名:オリックス・クレジット)や、ジャックスがこのような判断のもと不同意した例があります。)。
このような場合、給与所得者等再生で再申立するか、もしくは、現在の年収によれば、給与所得者等再生を利用しても弁済率が上がらない場合には、債権者に対し、収入証明と共にその旨を丁寧に説明したほうが良いといえます。当事務所では、実収入を証明して説明したことで、不同意を撤回させた例があります。
反対する方針で全件対応している債権者がいる場合
この場合、事前に意向調査したり、弁済率を交渉しても意味がありません。最初から給与所得者等再生の申立てを行うか、もしくは反対する債権者が過半数に達しないように先に一部弁済してしまうなども考えられます(ただし、申立人自身の財産から支払うと偏頗弁済と評価されます。)。
4 まとめ
個人再生手続きにおける不同意意見の主な理由は、以下の3つが挙げられます。
個人的感情や借入、返済状況を考慮した個別判断による、
弁済額の増額を期待しているから
反対する方針で全件対応しているから
金融機関や貸金業者は通常、個別の案件に対して意見を表明しませんが、短期間で高額借入を行った場合などは反対される可能性があります。
また、弁済額が低いと感じる債権者は、弁済額の増額を求めて反対意見を出すこともあります。特に大手業者の場合、給与所得者等再生によって弁済率が上がることを想定して不同意意見を提出することもあります。
不同意意見が過半数を超えると再生計画は認可されませんが、反対意見を撤回させるためには、個別に説明、説得することが功を奏することもあります。
さらにすすんで、事前対策として、個別の債権者に対して再生計画の内容や申立人の状況を説明して協力をお願いすることも考えられます。
どうしても協力が得られそうになく、かつその債権者が過半数の債権を有する場合には、給与所得者等再生を申立てる等の対策を検討する必要があります。
以上
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。