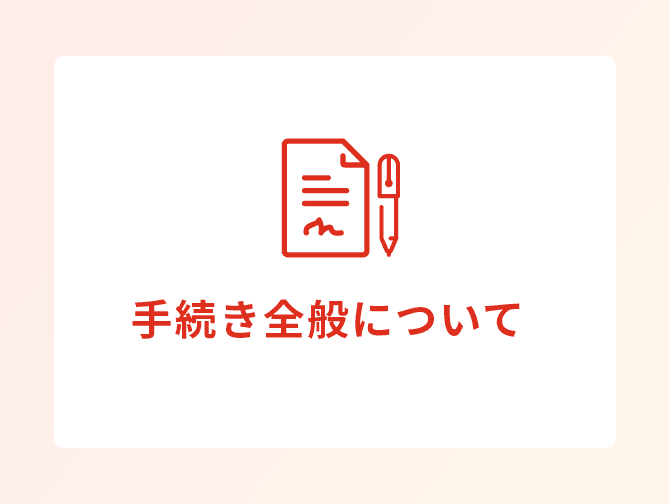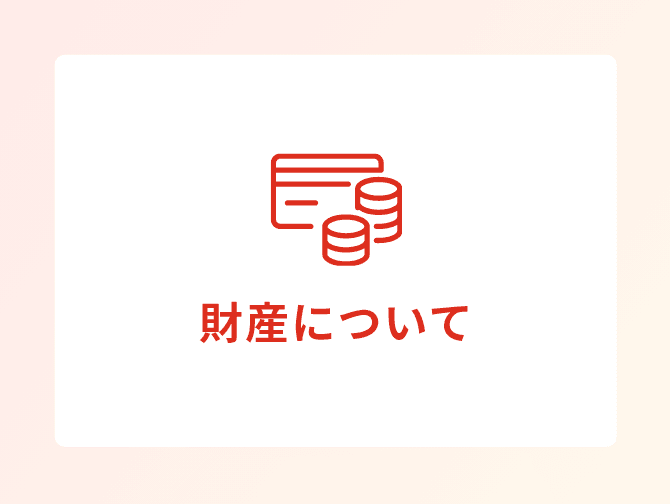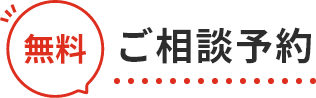個人再生委員はどこを見ている?(1 開始意見)
個人再生委員はどこを見ている?(1 開始意見)
〜当事務所の申立て事案から〜
はじめに
当事務所は関西圏を中心に、特に個人再生の申立て案件を多く取り扱っている法律事務所です。
従来、東京など一部地域を除けば、個人再生において個人再生委員(再生委員)が選任されることは非常に稀でした。
過去10年以上にわたり、選任率は3%程度といわれていました。
しかし、2021年以降、全国的に再生委員の選任率は徐々に上昇しています。
とりわけ大阪地方裁判所では、2023年度は選任率が約12%まで上がっているとの情報もあります(2024年度はさらに増え、24%にまで上昇しています。
その理由として、司法書士による申立事件の増加や、申立書に不備のある事件が増えている点が指摘されています(「月刊大阪弁護士会」2025年9月号より))。
当事務所では、難易度の高い案件や事業者による大型の申立ても多く取り扱っている関係もあり、再生委員が選任される割合は全件のうち30%を超えています。
再生委員が選任されると、申立資料に基づきさらに詳細な調査が行われ、手続きを開始しても問題ないかを1〜3か月程度で判断します。その調査結果は「意見書」というかたちで裁判所に報告されます。
本稿では、当事務所が扱った案件のうち、直近16件分の申立て事案をもとに、再生委員が申立て案件のどこをみて、何を調査・報告しているのかを分析し、ご紹介いたします。
(なお、今回は主に「小規模個人再生申立」手続きを念頭にご説明いたします。給与所得者等再生手続きの場合、小規模個人再生手続とは別の観点からさらに検討するべき事項もありますのでご了承ください。)
目次
第1 履行可能性の判断
第2 清算価値保障原則の確認
第3 債務の内容や上限額の確認
第4 その他の個別検討事項
第5 まとめ
第1 履行可能性の判断
1-1 家計収支の状況
意見書の最後に記述されることが多いものの、最も重視されるのが履行可能性です。
再生計画の履行可能性を判断するうえで、家計の収入と支出が適正かつ継続的に管理されているかが重視されます。
以下の項目が詳細に確認されます。
• 収入の内訳:給与、事業収入、賞与、配偶者の収入、親族からの援助など
• 支出の内訳:生活費、臨時支出、積立の状況など
個人事業者の再生案件で事業収入の変動性を検討したり、一時的な支出の増加がある事案では支出が浪費に該当しないことを確認するなど、個別事情を丁寧に検討している例もあります。
1-2 積立の状況
申立て後の積立状況や、弁済資金の確保が適切に行われているかが確認されます。たとえば、一時的に積立が滞った場合でも、その原因が「給与差押え」などやむを得ない事情かどうか、合理的な事情があるのかが考慮されます。
1-3 臨時支出への対応力
自動車保険料、学費、服飾費など突発的な支出があった際、それに対応できる繰越金や積立金があるかどうかも評価の対象です。
当事務所の場合、あらかじめ想定される臨時支出については「予想家計収支表」を作成するなどして履行可能性が十分にあることを予め説明するなどの工夫を行っています。
1-4 弁済期間の妥当性
通常は3年とされる弁済期間について、4〜5年の延長を希望する場合、「特別な事情」の有無が問われます。
たとえば事業収入の不安定性や税負担の増加、親族援助の継続性などが挙げられます。やや地域色があり、大阪をはじめとする関西圏では、延長について慎重な姿勢(節約等で家計改善の努力を十分行っているか)を示すことがあります。
第2 清算価値保障原則の確認
2-1 財産の評価と確認
清算価値保障原則とは、再生計画による弁済額が、再生債務者の手持ち資産(清算価値)を上回っていることを求める原則です。
近年、特に不動産価格の上昇により、自宅の価値が残ローンよりも相当高額が見込まれ、弁済額を上回る不動産を所有している事例が増えており、慎重に検討されるようになっています。
• 提出された財産目録の正確性(資料との照合や補充調査)
• 不動産、(事業者)什器備品、貸付金などの資産の評価額の妥当性(相見積、貸金のこれまでの請求経過、訴訟報告など)
これらについて、再生委員は独自に再評価を行うことがあります。
2-2 否認対象行為の確認
再生手続き開始前の偏頗弁済や特定の財産処分については、すでに再生債務者の手元からなくなっていても、清算価値に加算するべき必要性があるかを確認されます。
たとえば、親族からの借入返済や、支払停止後の親族への貸付が問題視された事案が複数存在します。
第3 債務の内容や上限額確認
3-1 再生債権の総額の確認
個人再生では、債務の総額が法律で定められた上限(住宅ローンを除き5000万円)を超えていないかを確認します。
超えていた場合は、手続の適格性を欠くため、再生手続が認められない可能性があります。
3-2 住宅資金貸付債権の取扱い
「住宅資金特別条項」を用いる場合には、以下の点が再生委員によって確認されることがあります。
• 該当債権の性質や使途(住宅ローンが住宅購入資金に使用されていない疑いがある場合)
• ペアローンの場合の単独申立ての可否(大阪の場合、同時申立てが原則であり、単独申立てをした場合には再生委員に意見を求めることになる。)
第4 その他の個別検討事項
申立て内容に応じて、再生委員が追加的に検討する事案もあります。
4-1 夫婦での同時申立て
ペアローンを組んだ夫婦の同時申立てにおいて、財産評価、履行可能性の点から夫婦共通の再生委員が選任されたケースがあります。
この場合、家計を一体的に評価し、弁済可能性が判断されます。
4-2 詐欺被害による請求権
再生債務者が詐欺の被害に遭っていた場合、その回収可能性や、返還請求額の評価が検討対象となることがあります。
4-3 成人した子への支出
成人した子に対する学費や仕送りなどの支出が、扶養義務の範囲内かどうか、再生計画に無理がないかどうかも判断材料とされます。
4-4 副収入や援助の継続性
副業収入が勤務先に禁止されていないか、今後も定期的に就労が見込めそうかといった事項や、親族からの援助がある場合、今後も継続可能かどうかといった点も、履行可能性を判断する上で重要です。
4-5意見書提出期限の延長
大阪の場合、再生委員の選任から開始意見の提出まで1カ月~1カ月半程度の期限が設定されます。
しかし、財産評価のために時間を要する場合や、事業収支・家計収支に不安や不明点がある場合、申立後も引き続き状況を見据えてから判断することがあり、意見書の提出期限が延長されることがあります。
第5 まとめ
本稿では、再生委員が申立て事案においてどのような点を重視し、「開始意見書」にどのように反映させているかを、当事務所での過去16件の実例をもとにご紹介しました。
再生手続においては、書面上の計画案のみならず、債務者の生活実態や家計管理能力、財産状況などが多角的に評価されます。
とりわけ再生委員が選任される場合には、形式的な審査だけでなく、実質的な生活再建の可能性が厳密に見られる傾向があります。
比較的問題のない事案でも1カ月、履行可能性に不安を持たれたり、財産調査に時間を要する事案であれば3カ月程度開始まで時間がかかることがあります。
その間、再生債務者は、月々の収支を管理報告しつつ、指示された財産資料や追加の調査に協力する必要があります。
開始決定までの調査は、再生手続で一番重要な時期といえます。
再生委員からあらかじめ聞かれそうな事項については先に調査や準備をしておき、できる限り早期に開始決定の判断が出るように対応したほうが良いと言えます。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。