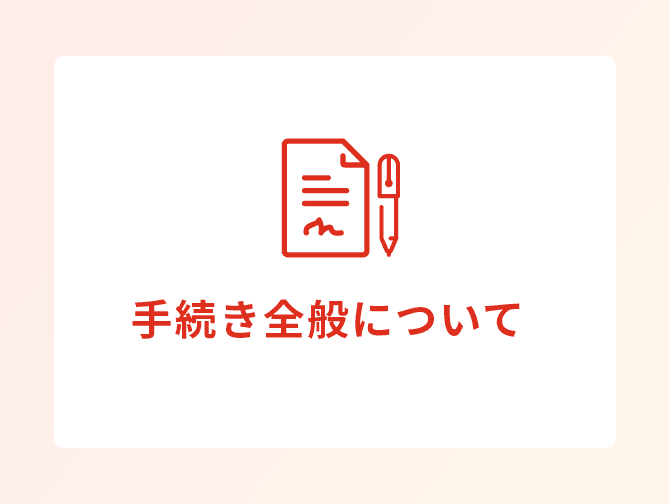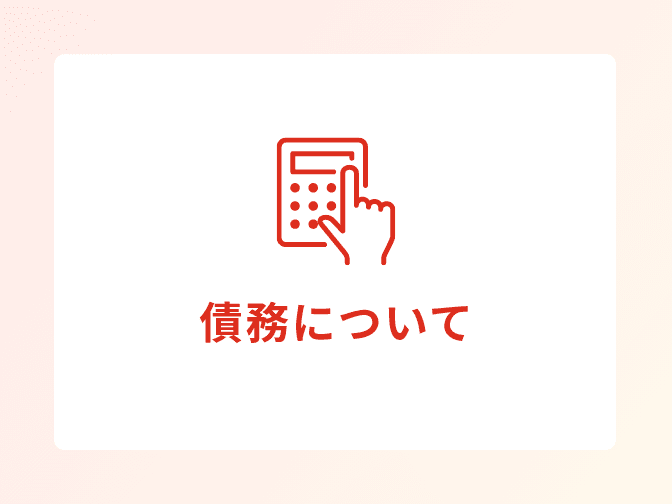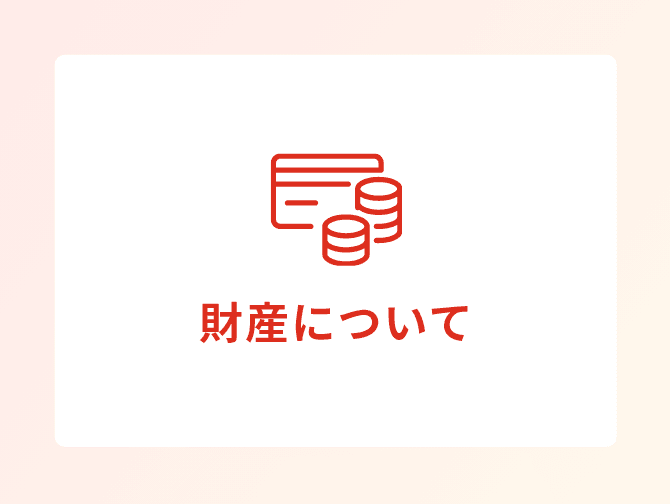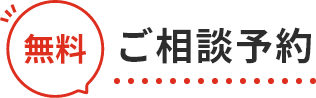個人再生委員はどこを見ている?(2 書面決議)
再生委員はどこを見ている?(2 書面決議)
~当事務所の申立て事案から
はじめに
従来、個人再生で再生委員が選任されることは稀でしたが、2021年以降、選任率は全国的に上昇傾向にあります。
当事務所では複雑な案件も多く、再生委員が選任される割合は約30%に上ります。
選任後は申立資料に基づき調査が行われ、その結果は「意見書」として裁判所に報告されます。
前回は、開始意見において、再生委員は何に注目し、どのようなことを調査し判断するのかをご紹介しました。
今回は、手続き開始決定後、再生計画案の提出後に行われる「書面による決議」の審査について、当事務所の申立て実例をもとに、その検討事項をご紹介します。
(なお、今回は主に「小規模個人再生申立」手続きを念頭にご説明いたします。給与所得者等再生手続きの場合、小規模個人再生手続とは別の観点からさらに検討するべき事項もありますのでご了承ください。)
目次
第1 付議意見の役割
第2 再生計画案の検討
第3 再生計画の履行可能性
第4 「特別の事情」の検討
第5 まとめ
第1 付議意見(意見書(書面決議))の役割
小規模個人再生では、申立代理人弁護士から再生計画案が裁判所に提出された後、債権者らに可否を問う「書面決議」に付するかどうかにつき、再生委員に意見を求めます。
このときに再生委員が提出する意見書には「意見書(書面決議)」と記載されます(以下では「付議意見」といいます)。
付議意見では、主に再生計画案の適法性と、その遂行可能性(履行可能性)が詳細に検討されます。
提出された再生計画案は民事再生法の規定に適合しているか、債権者の利益を害さないか、
そして計画された弁済が将来にわたって確実に行われるかという観点から多角的に評価されます。
以下に、検討される主な点を挙げます。
第2 再生計画案の検討
2-1不認可事由の不存在
民事再生法に定められた不認可事由(例えば、再生計画が法律の規定に適合しない、遂行される見込みがない、債権者の一般の利益に反する、不正な方法による成立など)に該当する事情がないことが確認されます。
2-2最低弁済額の要件を充足しているか
小規模個人再生では、住宅資金特別条項の対象債権(住宅ローン)を除く再生債務総額に応じて最低弁済額が定められています。
500万円以下の場合には一律100万円、500万円より高く1500万円までは5分の1、1500万円より高く3000万円までは一律300万円、3000万円より高く5000万円以下は10分の1です。
再生計画案ではこの要件をクリアしているかどうかがチェックされます。
2-3清算価値保障原則の遵守
再生計画案による弁済総額が、債務者が破産した場合の配当額(清算価値)を上回っていることが確認されます。
あくまでも実感ですが、再生委員が選任される事件の80%程度は、「清算価値保障原則」についてなんらかの検討事項があり、慎重な判断が必要になるものが多いです。
自宅不動産価値が残ローン額を上回っている方、申立前の偏頗弁済について心当たりのある方は、再生委員選任の可能性を想定しておいたほうが良いかもしれません。
2-4財産目録の確認と評価
提出された財産目録の内容の正確性や、流動資産(貸付金、保険の解約返戻金、売掛金、賃借保証金など)や、固定資産(自動車、不動産、営業用備品)の評価額の妥当性について、再検討が必要になることもあります。
2-5否認対象行為の有無
開始要件段階で検討された偏頗弁済(へんぱべんさい)や特定の処分行為(例:知人へ中古車を無償譲渡するなど)について、清算価値への加算の必要性が再確認される場合があります。
2-6再生計画案の形式的要件(記載の不備はないか)
大阪の場合、再生計画案の提出時には、Word形式の文章体で作成される「再生計画案」とExcel形式の表計算シートで作成される「弁済計画表」の二種類をもとに計画案の適法性が吟味されます(このほか、「積立状況報告書」もあります。こちらは裁判所が履行可能性を判断するためのものです。)。
再生計画案に記載する住宅資金貸付債権、物件目録、抵当権目録の記載方法には裁判所のルールがありますので、そのルールに則った記載かどうかが再生委員によりチェックされます。
弁済計画表にも免除率、返済方法(期間、分割、頭(あたま)金の有無、一括弁済)の記載に関するルールがありますので、間違いがないか、入念にチェックされます。
大阪地裁(本庁)の場合には、この形式要件については、裁判所と再生委員の両方が確認することとなっています。
第3 再生計画の履行可能性
再生計画案に定められた弁済を将来にわたって継続して行えるかどうかが詳細に検討される、最も重要な項目の一つです。
家計収支表を再確認し、今後三年から五年にわたる返済を続けられそうか判断されます(個人事業主の場合は、事業収支実績も検討します。)
3-1積立状況
再生手続開始決定以降の積立の継続性や、弁済原資の確保状況が評価されます。
給料の差押えにより積立が一時的に行われていないケースでは、その理由が考慮されます。
なお、開始後に積立が途絶えた事案では、なぜ積立しなかったのか(出来なかったのか)、遅れたとしても積立出来ているか、今後積立が遅れる危険はないかを慎重に判断されます。
開始意見と違い、付議意見は提出期間を延長して判断を留保することができません。
開始後に業績不振などで積立が途絶えた場合、再生計画の認可はかなり厳しくなると考えておきましょう。
3-2臨時支出への対応能力
予期せぬ支出(車険費用、学費、冠婚葬祭など)が発生した場合に、再生債務者が繰越金や積立金で対応できたかどうかが評価されることもあります。
また、開始要件の判断の際に今後の返済可能性について十分に検討された事案では、付議意見では詳しく検討しないことも多くあります。
付議意見でも履行可能性が再検討されるのは、①開始時にそもそもかなり履行可能性が苦しく、積立の継続が心配されていた事案、②事業収入の変動があるため、確実に収益を上げられているのか再確認が必要な事案が多い印象です。
そして、後述の③弁済期間を4年又は5年に延長する再生計画案を提出した事案では、その延長を必要とする「特別の事情」について検討が行われます。
第4 「特別の事情」の検討
大阪の場合、4,5年弁済を求める「特別の事情」はやや厳しめに判断されます。理由なく安易に5年弁済を求めても認められません。
(このあたりは、各裁判所に応じて厳しさに差があるように思われます。)
3年弁済だと支払が難しいが、4年(または5年)だと十分に返済できるという、きわどい経済状況であることが見込まれるので、家族の収入や支出の妥当性などを詳細に検討されることが多いです。
これまで、特別の事情が認められた例では、事業収入の不安定性、将来の税負担増加、臨時支出の必要性、親族からの援助の継続可能性、そして新型コロナウイルス感染症による事業への影響などが考慮されて延長が認められた例があります。
これらの検討を通じて、再生計画案が適正かつ実現可能であると判断されれば、書面決議に付されることになります。
第5 まとめ
個人再生において、「付議意見」の提出時期は、再生計画案の適正さと実現可能性を判断される重要な局面です。
再生計画案が法律に適合しているかどうか、最低弁済額や清算価値を満たしているか、そして何より、今後継続的に返済ができるかが入念にチェックされます。
積立の状況や家計収支に加え、想定外の出費にも対応できるかどうかが注目されることがあります。
弁済期間を延長する「特別の事情」については、各裁判所や地域差があるものの、3年では返済が難しいが延長すれば可能であるという事が説得的に理解できる事情が示せているかが重要です。
再生委員の視点を意識することで、より効率的な申立準備ができるようになります。
本記事が、手続に関わる皆さまの実務に少しでもお役に立てば幸いです。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。