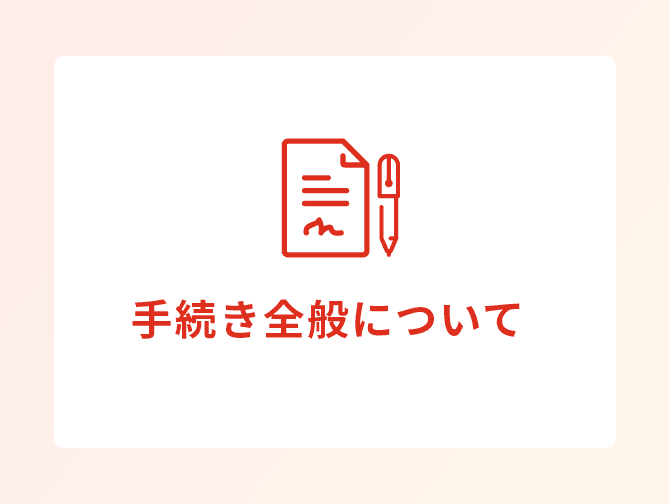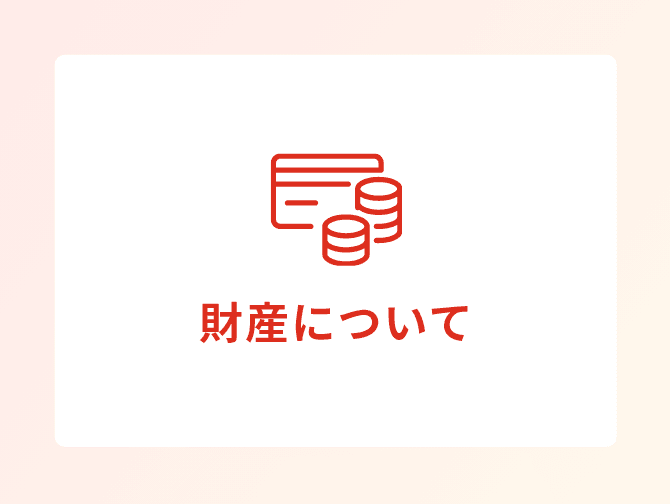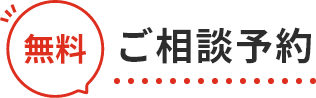個人再生委員はどこを見ている?(3 認可意見)
再生委員はどこを見ている?(3 認可意見)
~当事務所の申立て事案から
はじめに
従来、個人再生で再生委員が選任されることは稀でしたが、2021年以降、選任率は全国的に上昇傾向にあります。
当事務所では複雑な案件も多く、再生委員が選任される割合は約30%に上ります。
選任後は申立資料に基づき調査が行われ、その結果は「意見書」として裁判所に報告されます。
前々回、前回と、それぞれ開始決定、書面決議決定において、再生委員は何に注目し、どのようなことを調査し判断するのかをご紹介しました。
今回は、いよいよ最終の意見(認可意見)の審査について、当事務所の申立て実例をもとに、個人再生委員が検討した事項をご紹介します。
(なお、今回は主に「小規模個人再生申立」手続きを念頭にご説明いたします。給与所得者等再生手続きの場合、小規模個人再生手続とは別の観点からさらに検討するべき事項もありますのでご了承ください。)
目次
第1 認可意見の役割
第2 認可要件の検討項目
第3 まとめ
第1 認可意見の役割
小規模個人再生では、書面による決議を経て、債権額又は頭数で過半数の債権者の不同意が無ければ、ほぼ認可されます。
認可意見は、債権者の意見聴取期間経過後に個人再生委員から裁判所に提出される書面です。
平均的に見ると、認可要件に関する意見書は、開始要件に関する意見書と比較して記述量が大幅に少ない傾向にあります。
多くは、認可に必要な要件が満たされており、不認可事由がないことを簡潔に述べる形式がとられています。
以下に、検討される主な点を挙げます。
第2 認可要件の検討項目
2-1不認可事由の不存在
民事再生法に定められた不認可事由(例えば、再生計画が法律の規定に適合しない、不正な方法による成立など)につき、該当する事情が「ない」ことが確認的に記載された意見書がありました。
2-2再生計画の履行可能性の再確認
開始決定以降も、再生計画に定められた弁済を継続して行える見込みがあるかを確認される場合があります。
この場合、家計収支の状況、積立状況、臨時支出への対応能力などを評価したうえで、意見書に記載されます。
ただ、見込みが厳しい申立の場合、まずは開始意見の提出前に不安となる点を指摘され続けます。
よって、付議意見(書面による決議)、認可意見で履行可能性が慎重に検討される案件はほぼありません。
1例だけ、約3ページにわたり、再生計画の履行可能性について「補足説明」を行っていた意見書がありました。
その意見書では、再生債務者の家計収入(給与、配偶者の給与、賞与の考慮)と支出を詳細に検討していました。
そのうえで、副業収入を除外した場合でも家計が維持可能であること、年末年始の住宅ローン計上による支出額の変動、過去の賞与の繰越金による家計の維持能力などを具体的に説明して、履行可能性がないとは言えないと判断していました。
第3 まとめ
多くの場合、認可要件の意見書では、上記第2-1、2-2の項目について簡潔に「問題ない」と結論が述べられることが多いです。
申立(あるいは再生計画)の適法性や、履行可能性の詳細な根拠の検討は、殆どの場合、開始要件の意見書において検討されています。
認可意見の分量としてはA4用紙のおおむね半頁以下の記述しかないもの、あるいは定型書式にチェックが入っただけのものも多くありました。
これは、すでに開始要件の段階で詳細な審査が行われているため、認可要件の段階では簡潔な確認にとどまるケースが多いことを示しています。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。