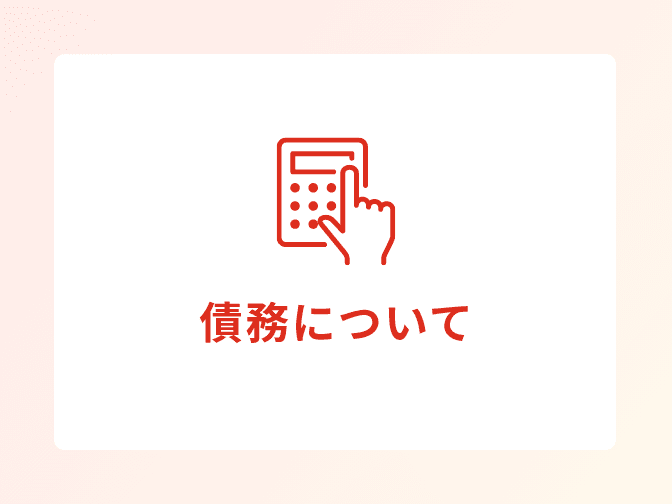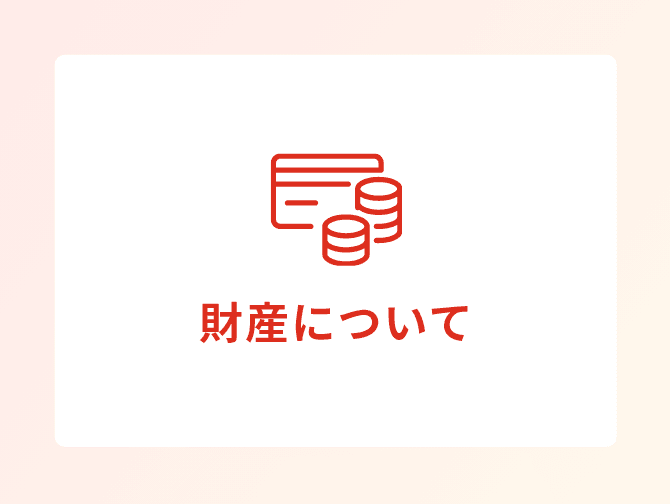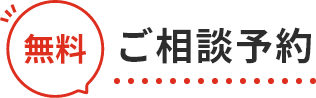債務「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
債務「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
【特別編】「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
当事務所では、これまで数多くの再生手続を希望される方のご相談を受けてきました。
そのなかには、専門家の立場からすると「そんなことまで心配されているのか」と思うような、意外な質問をいただくこともあります。
そうした質問に対しては、一つひとつ丁寧に説明し、誤解を解き、不安を和らげることを大切にしています。
また、同じ質問が繰り返されるということは、それだけ多くの方が同じ疑問や不安を抱えているのではないか、ということに気づかされました。
そこで今回、再生制度に関して、相談の際に実際に受けた質問と回答をまとめました。
「自分も同じ疑問を持っていた」「そんな考え方もあるのか」など、色々な受け止め方があると思いますが、参考にしていただければ幸いです。
今回は、第4回 債務の性質や債権者対応に関して、質問と回答例をご紹介します。
第4回 債務に関して
質問一覧
【1 収入に応じて返済条件が変わる?】
Q 債権者によっては、現在の収入ならもっと返せるはずだとか、弁済中に収入が上がったら、返済金額を上げろなどと要求されないでしょうか。
A 基本的には要求されませんが、認可時には注意が必要です。
債権者は、個人再生の各案件について、申立人の収入や資産を個別に精査することはほとんどありません。
ただし、債権者が把握している収入に比べて弁済率が低い場合には、「給与所得者再生ならもっと返済できるはず」と判断して不同意にすることがあります。
当事務所の実例では、これまで不同意意見を出した債権者として、楽天カード、ドコモファイナンス(旧オリックスクレジット)、その他一般の個人債権者などがあります。
他事務所の報告では、ジャックス、アコム、アイフルなどが反対した例もあります。
(いずれも「小規模個人再生申立」における債権者の対応です。)
一方、再生計画が認可されれば、その後に年収が増えたり、臨時収入があっても、再生計画は変更されません。
つまり、後から「返済を増やせ」と求められることはありません。
【2 最近借りたばかりの債権者は反対する?】
Q 今年借りたばかりの債権者がいます。再生計画に反対されますか。
A 反対されない可能性が高いです。
債権者は、単に「借入時期が最近だから」という理由で反対することはあまりありません。
それよりも、
- 再生計画が否決された場合に破産手続に移行してしまうか
- 給与所得者再生として再申立が行われる可能性があるか(=返済額が増えるか)
といった点を重視して態度を決めます。
ただし、親族・知人などの個人債権者の場合は、感情的理由で不同意意見を出すことがあるのでご注意ください。
【3 延滞していると反対される?】
Q 返済を延滞していたら、再生計画に反対されますか。
A 再生計画に反対されない可能性が高いです。
債権者は、反対しても議決権の割合によっては計画を否決できない場合も多いため、延滞そのものを理由に反対する例はほとんどありません。
したがって、延滞があること自体は大きな障害にはなりません。
【4 カードで購入した商品の扱い】
Q カードで買ったものは、全部持って行かれますか。
A 全て持っていかれるわけではありません。
債務整理後にカード会社などが物品の引き揚げを求めるのは、
- 債権者が有効な「所有権留保」を持っている
- 中古で再販売できる価値がある
場合に限られます。一般的に対象となるのは、
- 自動車、バイク
- スマートフォン(特にiPhone)やパソコン
- 事業用機械(冷蔵庫、空調機など)
といった高価な商品です。
衣類や家具、日用品などは、所有権留保の対象外もしくは、引き揚げても転売の可能性が低いため、引き揚げはほぼありません。
(ただし、一部の家電量販店系の債権者は、購入した家電、PCの状況を確認したうえで引き揚げを求めることがあります。)
【5 残なしクレカの扱い】
Q 利用残額のないクレジットカードは使ってもよいですか。
A 使わないでください。
個人再生の準備に入ると、支払いを停止した時点で信用情報機関に登録されます。
登録後は、現在残高のないクレジットカードでも、予告なく利用停止となることがあります。
また、弁護士に再生手続の準備を依頼し、他の債務の返済を止めているにもかかわらず、新たにクレジットカードで買い物をした場合、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として裁判所から問題視されるおそれがあります。
うっかり少額の利用であれば申立自体は可能ですが、多額または複数回にわたる場合には、再生委員による調査が行われたり、利用分を弁済額に上乗せするよう指示されることもあります。
最悪の場合、個人再生の申立て自体を断念せざるを得ないこともあるため、支払停止後はクレジットカードを絶対に使わないでください。
【6 マイカー通勤用の車両は?】
Q 通勤に必要なので、ローンで買った車だけは残したいのですが。
A 残せる可能性は低いです。
車をローンで購入した場合、多くの契約では「ローン会社が車の所有者のまま」という形(所有権留保)になっています。
そのため、返済ができなくなれば、ローン会社が車を引き上げるのが一般的です。
「どうしても車を手元に残したい」という場合は、ローン会社と話し合い、個人再生手続中にも返済を継続する「弁済協定」を結ぶ方法があります。
ただし、この方法が認められるのは非常に限定的で、たとえば次のようなケースに限られます。
- 仕事の継続に車が不可欠である
- 車がないと収入が途絶える
したがって、「通勤のために車が必要」という程度では、「電車やバスなどの公共交通機関で代替可能」と判断され、車を残すことは難しいのが実情です。
【7 通勤定期に使っているPiTaPaカード】
Q 通勤定期に使っているPiTaPaを残せますか。
A 後払いタイプのPiTaPaは残せません。
ただし、現金チャージ式の交通系カード(Suica、チャージ式ICOCAなど)は残せます。
お手元のカードがどのタイプかを確認し、後払い機能がある場合は利用を控えてください。
【8 給料は差し押さえられますか】
Q 給料は差し押さえられるのでしょうか。いつごろでしょうか。
A 債務整理に入っただけで、すぐに差押えが行われるわけではありません。
給与差押えは強制執行の一種であり、債権者が裁判所に訴訟を提起し、判決を得たうえで申立てる必要があります。
通常、訴訟の準備から判決、強制執行までには、少なくとも3か月程度の期間がかかります。
したがって、債務整理を始めた段階で直ちに給料が差し押さえられることはありません。
【9 滞納した税金の分割交渉】
Q 滞納した税金の分割交渉も弁護士にお願いできますか。
A 原則としてご本人に行っていただきます。
税金は、破産手続では免責されず、個人再生でも圧縮の対象になりません。
つまり、債務整理の対象外となります。
さらに、延滞が続くと、市役所や税務署が預金や財産の差押えにすぐ入る場合もあるため、再生申立てよりも先に対応する必要があります。
このような事情から、当事務所では、まずご本人に市役所・税務署等へ分割納付の申出をしていただき、そのうえで必要に応じてアドバイスを行う方針を取っています。
【10 住宅ローンは圧縮できる?】
Q 住宅ローンも他の借金と一緒に圧縮してほしいのですが。
A 住宅ローンは圧縮できません。
個人再生手続では、住宅ローン債権を他の債務と切り離して扱う特例(住宅資金特別条項)があります。
この制度の特徴は、住宅ローンについては返済を続ける代わりに、債権者が抵当権を実行せずに自宅を確保できるという点にあります。
そのため、住宅ローンを他の債務と同様に圧縮することはできません。
あくまで「住宅ローンはそのまま返済を続ける代わりに、他の債務だけを減額する」仕組みである点に注意してください。
【11 手続き中に本人が亡くなった場合】
Q 手続きの途中で、もし私が亡くなった場合はどうなりますか。
A 再生手続の段階によって異なります。
再生申立前、または申立後であっても認可決定が確定する前に亡くなられた場合、再生手続は廃止され、終了します。
この場合、債務は減額・免除前の状態で相続人に承継されます。
相続人は、
- 相続を放棄する
- 相続したうえで債務整理の対応を行う
のいずれかを選択する必要があります。
一方、再生計画の認可が確定した後に相続が発生した場合は、再生によって減額された後の債務が相続人に引き継がれます。
この場合も相続人は、
- 相続を放棄する
- 相続したうえで、減額後の弁済を継続する
のいずれかを判断しなければなりません。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。