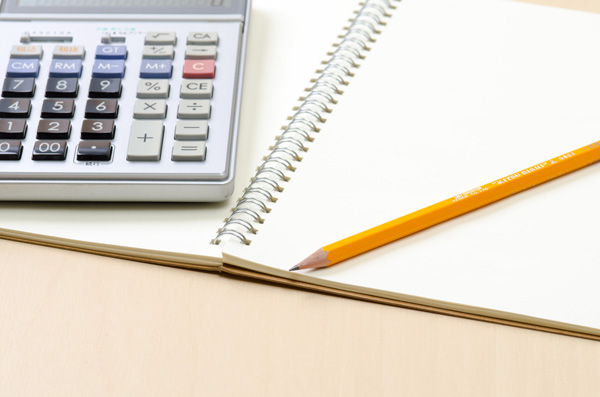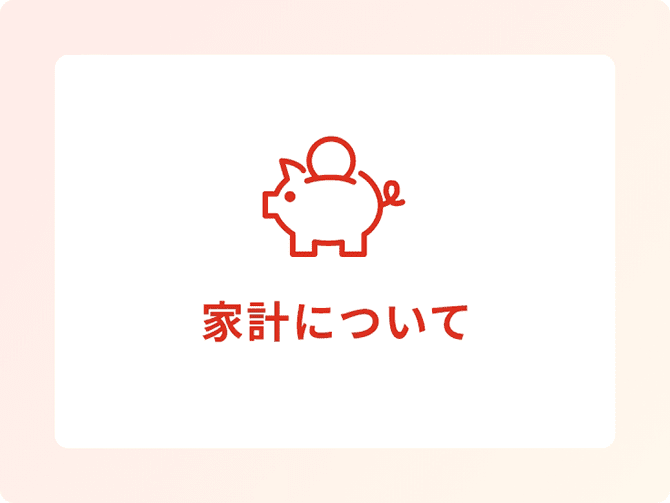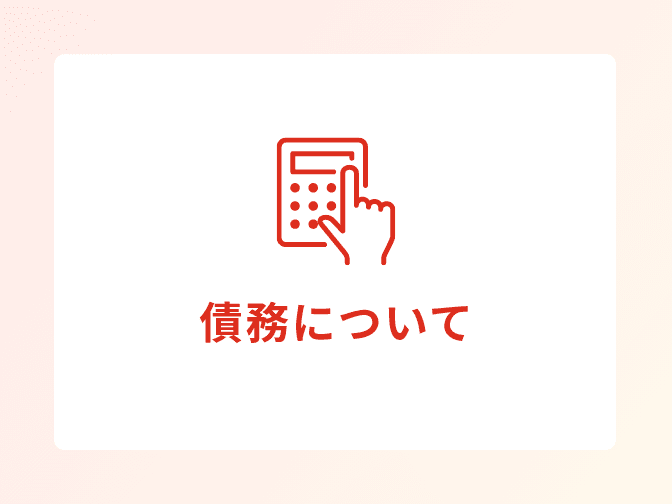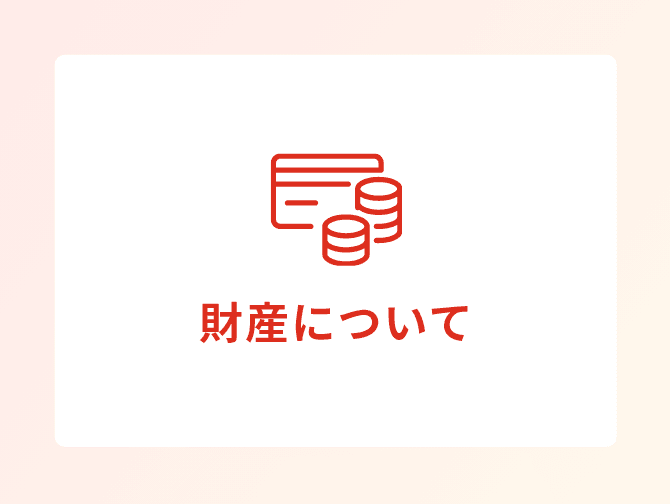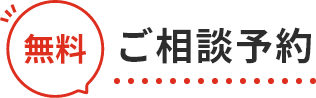収入/家計収支「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
【特別編】「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
当事務所では、これまで数多くの再生手続を希望される方のご相談を受けてきました。
そのなかには、専門家の立場からすると「そんなことまで心配されているのか」と思うような、意外な質問をいただくこともあります。
そうした質問に対しては、一つひとつ丁寧に説明し、誤解を解き、不安を和らげることを大切にしています。
また、同じ質問が繰り返されるということは、それだけ多くの方が同じ疑問や不安を抱えているのではないか、ということに気づかされました。
そこで今回、再生制度に関して、相談の際に実際に受けた質問と回答をまとめました。
「自分も同じ疑問を持っていた」「そんな考え方もあるのか」など、色々な受け止め方があると思いますが、参考にしていただければ幸いです。
今回は、第1回 収入/家計収支に関して、質問と回答例をご紹介します。
第1回 収入/家計管理に関して
質問一覧
【1 就業開始前の再生申立】
Q:今は失業中ですが、内定はもらっています。すぐに個人再生の申立してほしいのですができますか?
A:個人再生の申立てはすぐにはできません。
個人再生を利用するためには、「今後も安定して収入を得られる見込み」があることが制度上の条件になります。
「内定あり」だけでは不十分で、実際に働き始めて、給料を受け取っていることが必要です。そのため、最低でも1~2か月のあいだ、給料を受け取り、実績を作ってから、個人再生の申立てを行うことが通常です。
【2 妻の収支を外した家計収支表】
Q:私の収入で十分に返せるので、妻の(夫の)収入は関係ないと思います。裁判所に提出する家計収支は、私だけの単独収支で作成してよいですか?
A:それはできません。
個人再生手続では、同居している家族の収入も合算して判断されます。なぜなら、同居家族がいるかどうかで、生活に必要なお金が変わってくるからです。
裁判所は、家族の収入と支出を合わせて見ることで、「実際に返済できる余裕があるか」を判断します(さらにいえば、家族の使い過ぎが債務原因になっているケースもあります)。
そのため、配偶者の収入や配偶者以外の家族の支出も必ず申告しなければなりません。
【3 収入に応じた弁済増額?】
Q:私の収支状況からだと、再生認可後の予定額を十分返せそうです。逆に「もっと返しなさい(計画弁済額を増額しなさい)」と裁判所から言われないでしょうか。
A:返済額を増額するように指示されることはありません。
個人再生では、あなたが持っているお金や預金、保険、積立金など、すべてを合計した金額(=清算価値といいます)をもとに、最低限返さなければいけない金額が決まります。
この金額以上であれば、再生計画で決めた返済額で問題ありません。そのため、裁判所から返済額を増額するよう指示を受けることは基本的にはありません。
(※小規模個人再生の場合。給与所得者等再生を利用する場合は別です。)
【4 高収入の配偶者がいる】
Q:夫(あるいは妻)は私より高収入です。家計収支表を提出したらバレてしまうと思います。収入を合算したらもっと返せるのになどと指摘されないでしょうか。
A:夫婦といえども、借入名義が違えば返済義務もそれぞれ個別です。互いに債務保証などしていない限り、一方が他方の債務を返済することは、少なくとも再生手続き上はありません。
ただし、ものごとには限度があります。
妻が夫のギャンブル債務を返済するために、短期間で多額の借り入れをして夫の債務だけ清算し、妻だけが個人再生(あるいは破産)するような場合などは、指摘を受ける可能性はあります。
【5 フリマで再生】
Q:本業の収入だけだと返済が難しいです。しかし、私は、メルカリなどのフリマアプリで月10万円以上稼いでいます。この副収入を示して再生を通すことはできませんか。
A:安定、継続した副収入であれば考慮されます。
例えば、具体的な本業収入が18万円の場合:再生債務を3万円ずつ返すのは難しいことが多いです。
しかし、副業で毎月5万円あることを示せると、再生債務を返済する見込みがでてきます。
このうち、フリマアプリの場合は、なにを売っているのかポイントです。
自宅内の不用品売却による臨時収入であれば、安定、継続した収入とは評価されません。
仕入れ転売や、アクセサリーの自作販売等を行う場合には、一定の安定性、継続性を評価される場合もあります。
ただし、転売や自作販売を継続する場合には、一定額以上だと「個人事業」と評価されます。
個人事業者の場合、事業内容の説明のため、売上管理や仕入れ先の資料の提出を求められる可能性もあります。
この点は、申立前に弁護士とよく相談する必要があるでしょう。
【6 無申告、赤字でも個人再生できる?】
Q:私の仕事は建設業で、収入は全部手渡し、税金も納めていません。収入の証明が取れないですが、再生申立はできますか。
A:再生申立は無理ではありませんが、収入の証明方法について工夫が必要です。
・無申告は再生が通りにくい
個人事業者で税務申告が無申告のままだと再生認可の可能性は著しく低くなります。
・赤字申告又は所得が低い場合
確定申告が赤字の場合でも、車両など過去に購入した資産の減価償却費が大きい場合、専従者控除を利用している場合には、実際は黒字である事を示せる場合があります。
・改善のきざしがみられる場合
これまで、赤字又は十分な所得がなかったものの、最近収入や所得が大幅に上昇・改善したのであれば、再生認可の見込があります。
通帳への定期的な入金履歴や、経費記録等が証拠になります。
雇主や取引先に支払証明を書いてもらえるとさらに有利です。
最低でも、申立前6ヶ月分の収入記録を用意しましょう。
【7 修正申告、期限後申告】
Q:(6の続き)では、赤字の修正や、期限後にきちんと申告さえすれば再生は通りますか。
A:所得証明額が改善された場合、その副作用に注意してください。
過去の収支を正確に申告すれば所得があることを証明できる場合、昨年度分の確定申告を期限後に申告することで、再生の見込を上げられます。
ただし、一定の所得があることを申告すると、特に事業者の場合は、公的負担がぐっと増えます。
具体的には、増加した所得額に応じて、所得税、住民税あわせて15~30%(またはそれ以上)を追加で支払う場合が多いです。
また、国民健康保険料は、自治体により、数十万円単位の追納が必要にあることがあります。
仕入れ率の高い事業だと消費税申告が必要になることもあります。
このように、修正あるいは期限後申告をすると、過去年度の税金に対応しつつ、今年の税金も払いながら、さらに返済用資金の積立も必要になるのが通常です。
再生申立準備中に修正申告、期限後申告をする場合は、税理士、弁護士に相談したうえで行いましょう。
【8 妻が財布を握っている…】
Q:妻が私の通帳を握っているので、月々の家庭内の収支は把握しようがありません。このような場合に個人再生の申立てはできますか。
A:なんとかして収支を把握しましょう。
世帯の収入や支出がわからないままでは、個人再生の認可を受けるのは難しいです。
申立てをする際には、直近2か月分の「家計収支表」を提出する必要がありますが、家庭のお金の出入りが把握できなければ、家計収支表を作ることができません。
そのため、配偶者の方に事情を説明し、収入や支出の内訳を開示してもらえるよう協力をお願いしましょう。
【9 家族の力を合わせて…】
Q:私だけの収入だと返済予定額に足りません。妻(や成人した子どもたち)の収入を合わせたら何とか返せそうですが、それでも再生は通りますか。
A:認められる可能性はあります。
個人再生では「本人の収入」だけでなく「世帯全体の収入」で判断されることがあります。家族の収入と支出を合わせて、返済できると考えられれば、再生が通るケースもあります。
この場合、裁判所に対しては次のような資料や説明が必要です。
・配偶者の収入資料(給与明細、源泉徴収票など)
・配偶者以外の家族が安定して収入を得ていることの収入資料
・実際に家族の収入から返済にあてている実績、または今後の見込み
・同居していない親や子どもから援助を受ける場合は、「援助が続く見込みがあること」の説明
引き続き、再生計画案や制度全般に関する質問と回答例をご紹介していきます。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。