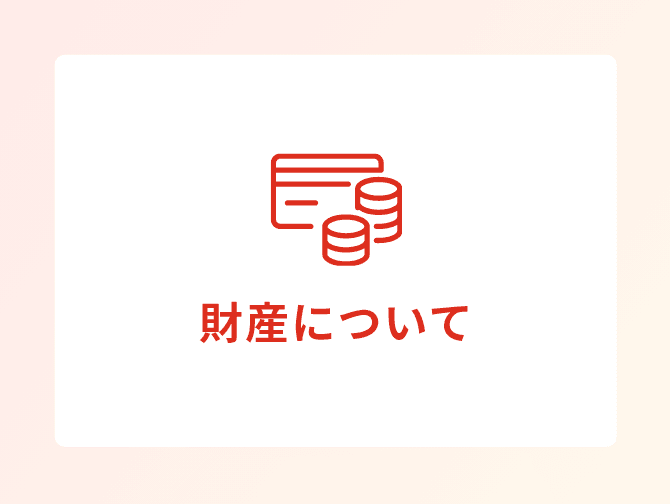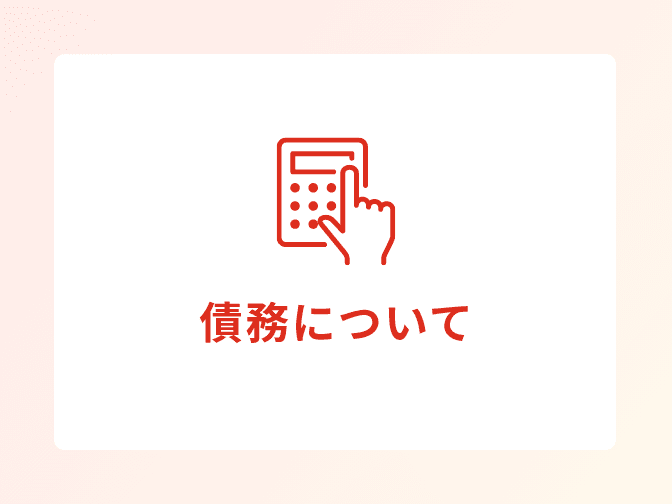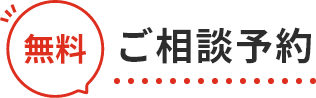財産「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
財産「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
【特別編】「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
当事務所では、これまで数多くの再生手続を希望される方のご相談を受けてきました。
そのなかには、専門家の立場からすると「そんなことまで心配されているのか」と思うような、意外な質問をいただくこともあります。
そうした質問に対しては、一つひとつ丁寧に説明し、誤解を解き、不安を和らげることを大切にしています。
また、同じ質問が繰り返されるということは、それだけ多くの方が同じ疑問や不安を抱えているのではないか、ということに気づかされました。
そこで今回、再生制度に関して、相談の際に実際に受けた質問と回答をまとめました。
「自分も同じ疑問を持っていた」「そんな考え方もあるのか」など、色々な受け止め方があると思いますが、参考にしていただければ幸いです。
最終回の今回は、財産に関して、質問と回答例をご紹介します。
第5回 財産に関して
質問一覧
【1 WEB通帳の提出方法】
Q 裁判所から通帳の提出を求められました。私の口座はWEB通帳ですが、どのように提出すればよいですか。
A 銀行が発行するPDFデータを原則として提出します。
近年は、ネット銀行だけでなくメガバンクでも紙の通帳を発行しないケースが増えています。
そのため、再生手続の際には、紙通帳がない場合でも「預金口座の取引履歴をPDF形式で出力したもの」を提出すれば問題ありません。
ご依頼者の方は、各銀行の取引明細データをPDFにして弁護士宛に送信してください。
ただし、CSVファイルは改ざんが容易なため使用しないでください。
PDFには、銀行名・口座名義人・口座番号が明記されていることが必要です。
履歴が短い場合や、取引明細に口座情報が表示されない場合は、口座情報画面のスクリーンショットで代用することもあります。
どうしてもデータ出力ができない場合は、銀行に依頼し、必要期間の取引履歴を郵送で取り寄せてください。
【2 団体加入の保険を調べるには】
Q 保険の証券番号や解約返戻金を調べるよう言われましたが、勤務先の団体で加入しているため内容が分かりません。
A 加入者証や案内資料を探し、パンフレットなどで確認してください。
会社や団体を通じて加入する団体定期保険(生命保険)や個人賠償保険(損害保険)などの場合、個人で保険会社に直接問い合わせることが難しいケースもあります。
しかし、加入年月日や加入者番号(証券番号)などの通知は必ず存在しますので、書類やメールを探してみてください。
また、多くの団体保険では解約返戻金が設定されていないため、パンフレットや社内の福利厚生サイトで内容を確認しましょう。
不明な場合は、勤務先の総務部に問い合わせるのが確実です。
【3 節約のため自動車保険を解約してよいか】
Q 家計が赤字なので、自動車の任意保険を解約して支出を減らしてもよいですか。
A 任意保険は絶対に解約しないでください。
任意保険は、車両補償だけでなく、人身事故や高額な物損事故の賠償責任をカバーする重要な保険です。
月々の保険料が数千円〜1万円程度であっても、解約によるリスクは非常に大きくなります。
再生手続き中に事故を起こした場合、被害者への賠償金が新たな債務となり、減免の対象外となるおそれもあります。
そのため、車を運転する限り、任意保険には必ず加入を続けてください。
どうしても支出を抑える必要がある場合は、車両保険を外す、より安価な保険会社へ切り替えるなどの方法を検討しましょう。
【4 家族の口座開示の義務はあるか】
Q 家族の通帳、たとえば妻や子どもの口座は見せなくてもよいですよね。
A 原則として不要ですが、例外もあります。
再生手続は本人の債務整理ですので、家族が連帯保証人等でない限り、家族名義の資産を開示する義務はありません。
ただし、家計収支表は家族全体で作成する必要があります。
そのため、家族の収入や支出が生活に大きく関係している場合、必要な範囲で通帳の一部を提出してもらうことがあります。
また、再生申立前に家族口座へ高額な送金が繰り返されている場合や、家賃・光熱費などを親名義の口座から支払っている場合は、家計資料として提出を求められることもあります。
この際、プライベートな箇所はマスキング(黒塗り)をして提出できます。
【5 賞与の使いみち】
Q 賞与を家電の買い替えや積立投資に使ってもよいですか。
A 再生準備を優先し、必要最小限の支出に留めてください。
個人再生中は、蓄財よりも返済が確実であること(履行可能性)が重視されます。
そのため、申立費用がまだ準備できていない段階で高額な支出をすると、再生計画が不安視される場合があります。
会社の持株会や確定拠出年金など、賞与から自動的に天引きされるものは、家計を圧迫しない範囲なら認められる可能性が高いです。
基本的には、賞与などの臨時収入は返済資金として確保しておきましょう。
【6 投資はすべて解約すべきか】
Q 株や投資信託は全部解約しなければなりませんか。
A 申立費用が不足している場合は解約してください。
個人再生では、一定の投資資産を持つこと自体は許されます。
ただし、投資資産の時価相当額は「清算価値」として計上され、最低弁済額に影響します。
清算価値が最低弁済額を超えると、弁済総額を増やす必要が出てくるため注意が必要です。
また、投資資産は価格変動があるため、再生計画の安定性を損なうおそれもあります。
できる限り、申立前には変動リスクのある資産を減らすようにしましょう。
【7 積立投資(NISA・iDeCo)はどうすべきか】
Q 積立NISAやiDeCoはやめた方がいいですか。
A 解約義務はありませんが、積立額の見直しをおすすめします。
積立NISAの残高は清算価値に含まれるため、金額が大きい場合は返済額に影響します。必要に応じて積立額を減らすか一時停止するのが望ましいでしょう。
一方、iDeCo(個人型確定拠出年金)は60歳まで引き出せない資産であり、財産目録には計上されません。したがって、返済総額にも影響しませんが、掛金が家計を圧迫していないか確認し、必要なら調整を検討してください。
【8 FX・仮想通貨を続けてもよいか】
Q FXや仮想通貨を趣味で続けたいのですが、再生中でも可能ですか。
A 直ちに中止してください。
FXや仮想通貨は値動きが激しく、生活を不安定にさせる投機的取引です。再生準備中に継続していると、裁判所から不誠実な申立てと判断されるおそれがあり、申立却下や個人再生委員選任の原因になります。
また、債権者からも「投資できる余裕があるなら返済に回すべき」と受け取られ、再生計画の同意を得にくくなる場合もあります。したがって、弁護士が受任通知を送った時点でFX取引等は完全に中止してください。
【9 当せん金の扱い】
Q 再生中に宝くじや競馬で当たったらどうなりますか。
A 高額の臨時収入は返済額増加につながります。ギャンブル自体も避けてください。
再生手続中に高額の当せん金が出ると、預金額が増加した分だけ返済額も増える可能性があります。また、ギャンブル行為はFXと同様に「不誠実な申立て」と見なされ、手続に悪影響を及ぼすおそれがあります。したがって、再生中のギャンブルは絶対に控えてください。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。